
こんにちは!
パピチワ犬「おはぎ」と暮らしている飼い主です。
愛犬の吠えグセ、悩んでいませんか?
わが家でも、お迎えした当初は「インターホンが鳴るたびにワンワン」「外の物音に反応して吠える」「私たちが出かけようとすると遠吠え」など、吠える行動に困っていました。
特にマンションなどの集合住宅では、近隣への騒音も気になりますよね。
今回は、実際に私たちが試してみて「これは効果があった!」と感じた方法を中心に、吠えグセ対策を3つご紹介します。どれもお金をかけずに家庭内でできる方法ばかりなので、ぜひ参考にしてください。
吠えグセの原因って何?
まず大切なのは、「なぜ吠えるのか?」を知ること。犬は言葉で伝えられない代わりに、吠えることで感情や状況を伝えようとします。
代表的な原因には以下のようなものがあります。
- 見知らぬ人や音への警戒
- 飼い主がいなくなる不安(分離不安)
- 要求(遊んでほしい、おやつが欲しい など)
- 退屈やストレスの発散
- 周囲の環境音への過敏反応
吠えるたびに「ダメ!」と怒ってしまいがちですが、まずは「この子は何を伝えようとしているんだろう?」と一歩立ち止まって考えるのが第一歩です。
わが家で効果があった吠えグセ対策3選
① インターホン対策:録音音声で“慣れさせる”トレーニング
最初に困ったのは、インターホンに対する反応でした。ピンポンが鳴るたびに吠えまくるおはぎ…。
そのたびに私たちもイライラし、「静かに!」と怒ってしまう悪循環。
そこで試したのが、スマホでインターホンの音を録音し、何もない時間にランダムで再生する方法です。
最初は反応していましたが、毎日何回も“偽のインターホン音”を流していくうちに、「あ、これ鳴っても何も起きないな」と学んでくれました。
2週間ほどで、実際のインターホンにも落ち着いて対応できるようになりました。
② 外の音対策:カーテンを閉めて“見せない”工夫
おはぎは外の音や人影にも敏感でした。とくに夜、通行人の足音や車の音にいちいち反応して吠えてしまうことも。
そこで取り入れたのが、「見えない・聞こえない環境づくり」。
カーテンを遮音性の高い厚手のものに変え、夜間は早めに閉めるようにしました。また、夜はテレビやヒーリング音楽などをつけて「外の音を気にしない環境」を意識的に作りました。
それだけでもかなり落ち着いて過ごせるようになり、吠える頻度は激減しました。
③ 要求吠えには“無反応”を貫く
「吠えればかまってもらえる」と学習してしまうと、吠えがどんどんエスカレートしてしまいます。
わが家でも最初は「遊んでー」「おやつちょうだい!」の要求吠えに、つい応じてしまっていました。
でも、そこでぐっと我慢。吠えても何も反応せず、静かになったタイミングで声をかけるようにしました。
最初はかわいそうに感じるかもしれませんが、「吠えても無駄なんだ」と分かってもらえるまで、心を鬼にして一貫した対応が大切です。
吠えグセ対策で大事なのは「一貫性」と「根気」
犬のしつけはすぐに効果が出るわけではありません。
私たちも何度も失敗しながら、「どうやったら伝わるかな?」「今日はうまくいったかも!」と試行錯誤の連続でした。
でも、犬は飼い主の気持ちをよく見ています。怒鳴るよりも、冷静に一貫した対応を心がけたほうが、確実に伝わります。
吠えるたびに怒るのではなく、「吠える必要がない状況をつくる」「吠えない方が得だと学ばせる」ことを意識して取り組むと、少しずつ変化が見えてきます。
それでも困ったら…プロの力を借りるのも手段
どうしても改善が見られない場合や、吠え方が過剰で生活に支障が出ている場合は、プロのドッグトレーナーや獣医師に相談するのもおすすめです。
特に分離不安や強い恐怖心など、根本的な不安や精神的な要因が隠れている場合には、専門家のサポートが非常に有効です。
わが家でも「一度カウンセリングを受けてみようかな」と思ったことがありました。愛犬と向き合うきっかけにもなりますし、専門家のアドバイスを受けるだけでも気持ちが楽になることがあります。
吠えグセに悩んでいると、「このまま一生続くのかな…」と不安になってしまいますよね。
でも、大丈夫。少しずつ、確実に変化は訪れます。
愛犬をよく観察し、適切な方法でしつけていけば、信頼関係も深まり、より安心できる毎日が待っています。
わが家のおはぎも、今ではインターホンが鳴っても無反応なときもあるほど。最初の頃からは考えられない変化です。
もしあなたも吠えグセに悩んでいたら、ぜひ今回ご紹介した方法を試してみてくださいね。
「うちの子にもできた!」という小さな成功体験が、きっと自信につながります。

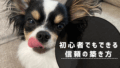
コメント